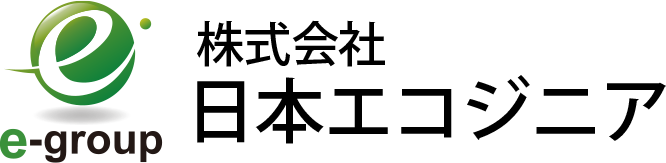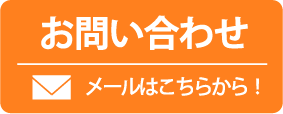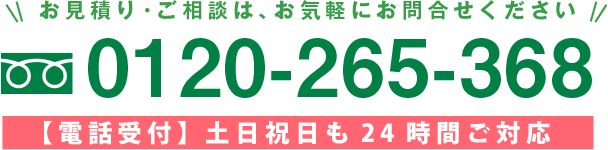初めての家屋解体で失敗しないために知っておくべきこと
私の家、補助金の対象になる?
補助金の対象になりやすい家の条件についてお話しします。
まず初めに、解体したい地域に補助金制度があるかどうか、事前に確認することがとても大切です。そもそも補助金を支給していない自治体もあります。その場合は残念ながら補助金を受けることができません。必ず事前に自治体へ確認しましょう。
では、補助金を受けやすい条件を3つご紹介します。
1. 物件の条件
- 一定期間使用されていない空き家であること
- 対象の市区町村内にあること
- 倒壊や悪影響を及ぼす危険性があると判断されること
2. 申請者の条件
- 空き家の所有者であること
- 市税の滞納がないこと
※以前に同じ補助金を受け取っている場合は、再度受け取れない可能性があります。ご注意ください。
3. 工事の条件
- 空き家の全部を解体すること
- 対象地域内の業者に工事を発注すること
基本的に補助金の申請は工事着工前に行う必要があります。すでに着工している工事は対象外になるのが一般的なので、必ず事前に確認を!
自治体によって細かい条件は異なりますが、今回ご紹介した内容は多くの自治体で共通している「一般的な条件」です。
補助金は後払い?本当?
はい、補助金は後払いです。
つまり、解体工事がすべて終わったあとに補助金が支給されます。
したがって、まずは全額自己負担で解体費用を工事会社に支払う必要があります。
工事完了後には「解体工事完了実績報告書」を自治体に提出します。これは、自治体が工事内容や金額を確認するための重要な書類です。提出を忘れると補助金が受け取れなくなるので、注意が必要です。
報告書提出後、約2〜3週間後に補助金が支給されるのが一般的です。
補助金受け取りまでの流れ
- お申し込み
- 申請手続き
- 審査
- 採択
- 工事開始
- 工事完了
- 実績報告
- 確定検査
- 交付(補助金の支給)
補助金の不正利用はNG!
補助金は目的以外での利用はできません。
申請後に工事内容が変更されたり、実際と異なる内容で申請してしまうと、検査で引っかかり、補助金を受け取れない可能性があります。
最終的な審査に通らない可能性もありますので、専門家や自治体へ何度も確認するようにしましょう。
木造2階建ての解体工事費用と補助金
解体費用は各自治体によってばらつきがあります。
補助金の支給額の相場は「解体費用の1/3または2/3、かつ上限50万円」というケースが多いです。
例えば、60坪の建物を補助金なしで解体すると、186万円〜390万円程度の費用がかかるのが一般的です。
補助金を利用すれば、自己負担額は136万円〜340万円程度に抑えられるかもしれません。
補助金を受けるための主な条件
- 空き家である
- 老朽化や破損が進んでいる(基準値を超えている)
- 耐震基準を満たしていない
- 解体後に再建築の予定がない
- 建物の所有者が申請者である
- 申請者の所得や資産が基準より低い
- 申請者が税金を滞納していない
注意すべき3点
- 自治体の予算には上限がある
- 申請は工事の着工前に行う
- 補助金は工事完了後に給付される
残地物の処理について
解体工事前に家の中に残っている不用品や廃棄物、いわゆる「残地物」は、可能な限りご自身で処分することをおすすめします。
理由としては、建物の解体により発生する廃材は「産業廃棄物」として処理されますが、家具や家電、生活雑貨などの残地物は「一般廃棄物」となるため、処分の区分が異なり、同時に処理することができないためです。
解体業者に残地物の処理まで依頼することも可能ですが、これは本来の業務とは異なるため、追加費用が高額になる場合もあります。場合によっては10万円以上かかることもあるため注意が必要です。
以下に、主な残地物の処分方法をまとめました:
- 日用品の処分方法
日用品(食器、衣類、書籍など)は、地域の分別ルールに従い、「燃えるゴミ」「燃えないゴミ」「資源ゴミ」として処分してください。 - 粗大ゴミの処分方法
タンス、ベッド、本棚などの大型家具は、自治体の粗大ゴミ回収に申し込み、指定日に出しましょう。 - 家電製品の処分方法
テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンの4品目は「家電リサイクル法」により、自治体のゴミとして処分できません。リサイクル券を購入し、指定引き取り場所へ持ち込むか、購入店に引き取ってもらいましょう。 - パソコンの処分方法
ノートPC・デスクトップPC・モニターなどは、メーカーの回収サービスや専門の回収業者を利用してください。プリンターやケーブル類は一部、粗大ゴミや一般ゴミで処分可能です。
ライフラインの停止について
解体工事前には、以下のライフラインの停止手続きを行う必要があります。
- 電気
- ガス
- 固定電話・インターネット回線
- テレビアンテナなど
これらの停止手続きは、原則として電話予約によって行います。解約時には以下の情報を確認されます:
- 解体する建物の住所
- 契約者名
- お客様番号(契約書などに記載)
- 連絡者の氏名と電話番号
注意点として、水道だけは解体工事中に使用するため、停止せずに残しておきましょう。解体時に出る粉塵を抑えるため、水を使って散水を行う必要があるためです。
予約は混み合うことも多いため、できるだけ早めに手続きを済ませておきましょう。
解体工事のクレーム対策
解体工事に伴うトラブルを防ぐためにも、事前の準備と対応が非常に重要です。よくあるクレームは以下の3つに分類されます。
- 騒音に関するクレーム
解体作業では大きな音が発生します。特に近隣に高齢者、小さな子ども、受験生がいる家庭では注意が必要です。作業可能時間は「騒音規制法」により、原則午前7時〜午後7時と定められています。 - 粉塵に関するクレーム
解体時には大量のほこりが舞います。洗濯物が汚れたり、車や家の中に粉塵が入ることもあります。散水や防塵シートの使用で対策を行うことが求められます。 - 重機に関するクレーム
道が塞がれたり、振動や騒音が原因で迷惑を感じる住民もいます。万が一、建物や車が傷ついた場合の補償体制についても、業者に事前確認しておくと安心です。
クレームを防ぐために最も重要なのは「業者選び」です。
丁寧に近隣への挨拶回りを行う業者や、クレームが出た際に迅速に対応してくれる業者を選びましょう。場合によっては追加費用がかかる場合もありますが、トラブルを未然に防ぐための大切な投資です。
万が一、対応してくれない業者を選んでしまった場合は、消費生活センターや行政の建築相談窓口に相談することもできます。
比較サイトや業者選びの注意点
近年、解体工事の比較サイトや一括見積もりサービスを利用する方が増えています。便利な反面、以下のような注意点もあります。
- 見積もりは一括取得できるが、断るのは自分自身で行う必要がある。
- 紹介された業者とのトラブルに、サイト運営会社は原則介入してくれない。
- 近隣住民とのトラブルに関しても、対応してくれるとは限らない。
サイトの評価が高い業者であっても、その評価がつくまでには実際にトラブルを経験した人も少なからずいた可能性があることを忘れないでください。
信頼できる解体業者を選ぶ際は、以下のポイントをチェックしましょう:
- 必要な許認可を保有しているか
- 安全対策・保険加入の有無
- 明確な見積もりと追加費用の有無
- クレーム対応・アフターサポートの有無
どれも当たり前のようで、実際には対応していない業者も存在します。価格が安すぎる業者には特に注意が必要です。
「安いから」と飛びついた結果、大きなトラブルに発展し、余計な費用がかかることのないようにしましょう。
まとめ:事前準備と業者選びで解体工事の成功を
家の解体工事には多くの準備と配慮が必要です。残地物の処理、ライフラインの停止、近隣への挨拶、信頼できる業者の選定等、これらをしっかり行うことで、不要なトラブルを避け、スムーズな工事につなげることができます。
初めてのことで不安な場合は、地域の専門業者や相談窓口を活用しましょう。私たちも、解体に関するご相談を随時承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。